
「入浴介助で足が蒸れることが多く、水虫になりやすいです」
「わたしも水虫に感染したらどうしよう」
仕事で水虫に感染するのは辛いですよね。入浴介助の現場は白癬菌が多い環境なので、不安を持ちながら働く看護師さんが多いです。でも、白癬菌に触れたら感染、発症をするわけではありません。
白癬菌の特徴と自分の足タイプを知れば、しっかりと感染予防ができ、入浴介助の仕事が不安なくできます。そこで今回は、入浴介助で水虫にならないために、自分でできる白癬菌対策を紹介します。
白癬菌(爪水虫)とは
白癬菌は生きているカビで、温度、湿度、栄養条件が整えば細胞分裂して増殖します。
<白癬菌が好む条件>
|
温度 |
適温は36℃(15℃~60℃でも生きられます) |
|
湿度 |
60%以上 |
|
栄養 |
タンパク質ケラチン 皮膚の表面を覆う角質層(垢となって落ちる場所) |
入浴介助の現場は、①高温②多湿③ケラチン(垢)が豊富な3条件すべてそろった場所で、白癬菌にとって住み心地の良いものです。高齢者になると足白癬や爪白癬になりやすく、利用者さんの皮膚からはがれ落ちた落屑を介助者が素足で踏んで、菌が付着するといった場面が多くみられます。
白癬菌は24時間以上経過しないと、角質中に白癬菌が侵入することはありません(傷がある場合は24時間以内に角質中に侵入します)。侵入後、さらに増殖して感染すると水ぶくれや足趾の間に皮がむけるなどの症状を引き起こします。
足に感染した「足白癬」が爪に侵入すると「爪白癬」になり、爪甲が混濁&肥厚して、爪切りケアが難しいです。治療方法は内服か外用薬ですが、併用禁忌薬や副作用症状(頭痛・胃腸障害)に注意が必要で、内服できない方は抗真菌外用薬を使用します。
入浴介助で足白癬になる人とならない人の違い
同じ入浴介助をしていても、白癬菌に感染する人としない人がいるのはなぜでしょうか?
| 足白癬になりにくい人 | 足白癬になりやすい人 | |
| 足趾の形 | 足趾が開いてすき間がある | 足趾と趾がピタッとくっついている |
| 履物 | 普段はサンダルや通気性の良い靴をはいて風通しがよい | 普段は革靴やブーツを長時間はいて蒸れやすい |
| 汗 | 普通~乾燥している | 汗をかきやすい |
| 病気 | なし | 糖尿病(手足の血行不良・感覚障害) |
感染が成立するのは、入浴介助後に足に残った菌が角質から入り込み、繁殖しやすい環境条件が整った時です。つまり入浴介助そのものだけではなく、自分の足の形状や普段履いているものも白癬のなりやすさに関係してきます。
足白癬の中で多いのは、趾間型足白癬といって足趾の間になる人です。足の趾と趾がピタッと密着するタイプの人は、その部位に汗が溜まりやすく、洗い残しや拭き忘れがあると、そこから白癬菌が繁殖します。
また仕事中や通勤に使用する靴が蒸れやすい人も要注意です。糖尿病の場合は皮膚症状に気づきにくく、菌に対する抵抗力が弱いので、足白癬になりやすい傾向があります。
入浴介助で足白癬にならない感染対策5つのポイント
入浴介助の現場は一年中白癬菌が活発な環境で、菌を避けることはできません。でも5つのポイントに気をつければ予防ができます。
1.洗い残しをつくらない
足趾がピタッと密着するタイプの人は、忘れがちな趾と趾の間をシャワーでしっかり洗い流してください。皮膚の表面に菌が付いているだけなら、石けんを泡立ててやさしく洗浄するだけで十分取れます。
2.趾と趾の間をふく
自分専用のタオルで拭いて、乾燥させてから靴下をはいてください。とくに、足趾と趾の間をふくのが大事です!面倒かもしれませんが、家の入浴後にも忘れずに拭いておくと予防になります。
3.足趾と足趾の間を広げる運動
趾同士がひっついている人は5本指ソックスがおすすめで、白癬菌の好きな湿気を予防します。休憩時間には、グーチョキパーの筋肉運動をして足趾を広げるストレッチをしましょう。そのときに足に傷がないかどうかチェックする習慣をつけるとよいですね。
4.あやしいなと思ったら皮膚科受診
くすりを使っても良くならないときは、他の病気かもしれません。受診がまだなら早めに診てもらって、完治しましょう。
<水虫と間違えやすい4つの症状>
|
常在菌の感染 |
皮膚の表面の常在菌が湿った趾間で増殖するただれ、悪臭 |
|
かぶれ(接触皮膚炎) |
じゅうたんや靴下、靴の染料などに触れて起こるかゆみ、発疹、水泡 |
|
汗疱性湿疹 |
手足に汗をかきやすい人に多い足裏の小水疱、皮むけ |
|
皮膚カンジダ症 |
足爪や趾へのカンジダ菌の感染趾間のただれ、爪周囲の炎症 |
5.バスマットとタオルは毎日洗濯する
バスマットやタオルは菌が繁殖する場所なので、こまめに取り換えましょう。菌は乾燥に弱いので、バスマットを十分に乾かすことで他に広がることが防げます。洗濯機で他の洗濯物と一緒に洗うことはOKですが、大事なことは乾燥をしっかりすることです。
まとめ
入浴介助終了後に足と足趾の間を丁寧に洗い、よく乾燥させていれば感染は予防できます。
上記の白癬菌対策をして、「水虫にならない」足環境を整えましょう。
ケアスタッフ
最新記事 by ケアスタッフ (全て見る)
- 入浴介助で水虫はうつるもの?介護のプロがしている白癬菌対策 - 2019年11月22日
- これって虐待?認知症ケアで後悔しないためのチェックリストと対処方法 - 2019年10月10日
- ナースが混同しやすい用語「自立支援介護」と「自立支援医療」の話 - 2019年7月10日
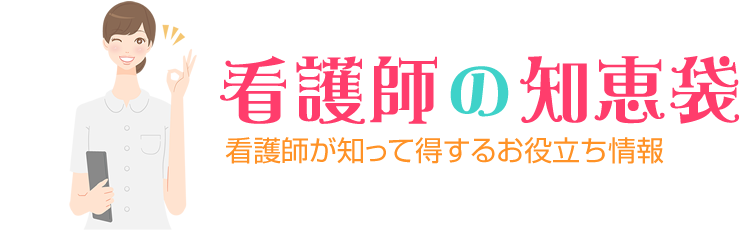
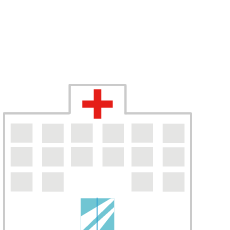


 職場を変えた話
職場を変えた話 看護力向上いいんかい
看護力向上いいんかい 看護のお悩み相談室
看護のお悩み相談室 ホット一息 トレンド広場
ホット一息 トレンド広場