
「もしかして認知症かもしれない」と疑ったとき、認知症検査といえば「長谷川式認知症スケール」を思い浮かべる医療者の方々が多いかと思います。
認知症は早期発見が大切ですといわれていますが、もし私が突然!テスト形式で、しかも密室で「認知症の検査を受けますよ」といわれたら。きっと緊張したり、「早く終わってほしいな。」「やりたくないな。」と感じることでしょう。
それと同様に高齢者も同じ気持ちです。そのため認知症の検査で最もナースが意識しておくことは、対象者の精神的な配慮になります。
検査時の「不安な気持ち」や「疲れ」に気を配りながら適切な質問ができる5つのポイントをご紹介いたします。
長谷川式認知症スケールってなに?
高齢者の中から認知症高齢者をスクリーニングする検査のことです。
43年前に長谷川和夫先生が開発し、現在は1991年に改訂された「改訂 長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R:Hasegawa dementia rating scale-revisedの略)」が、日本の病院や高齢者施設などで広く使用されています。
検査内容は9設問からなります。「今日は何年何月何日、何曜日ですか?」といった記憶に関する質問に回答してもらい、認知症か否かを判定します。
判定は30点満点中20点以下が認知症の疑いがあると考えます。
また総合点の結果のほかに、どのような認知機能が低下しているかも把握できるようになっています。
各設問で把握できること
・問1 名前の見当識 自分のことや、自分が置かれている状況認識をみます。
・問2 日付の見当識 目的やスケジュールなど計画を立てられるかなどの遂行機能もみます。
・問3 場所の見当識 これが答えられないとき、不穏やせん妄などの症状も合わせて注意してみてください。
・問4 聴覚性記憶 耳から聞いた新しいことを覚える能力をみます。サイレンがきこえてもサイレンと分からなくことと関連します。
・問5 知的能力 順序立てる能力をみます。料理をつくることなどと関連します。
・問6 記憶と作業 記憶を保持する能力と並行して作業ができるかをみます。
・問7 聴覚性記憶 記憶を保持する能力と物事を結び付ける能力をみます。
・問8 視覚性記憶 眼で見た新しいことを覚える能力をみます。道に迷いやすくなったり、同じものを買ったりすることを関連します。
・問9 言語の流暢性 知識量ではなく、言葉のスラスラでてくる程度をみます。
メリットは、ベッドサイドで行うことができ、5分程度の短時間で評価できます。
デメリットは、言語的な質問でやりとりしますので難聴の方や失語症の方はハードルが高いです。また動作性の認知機能は評価できません。
改定 長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)(表1)
http://www.medica-site.com/special/img_special069/hasegawa.pdf
長谷川式認知症スケールで配慮する5つのポイント
1)本人の了解を得て、はじめと終わりを大切に。
「認知症の検査をします。」といきなり言うと高齢者は構えてしまいますので、「最近物忘れが気になったり、不安なことはありませんか」と前置きをしてから、長谷川式スケールの説明をして了解を得ましょう。
終了時も、「疲れましたか?」など世間話をして、検査の嫌な気分のまま終わらないようにしてあげましょう。
また人によっては、「こんな簡単な質問を聞いてきてバカにしているのか」と自尊心を傷つけたり、そもそも質問されること自体が苦手な方もおられます。
実施頻度は、リハビリ目的で何度も行わないことです。年に1回程度かもしくは特別にしなければならないときのみです。
テストを受けさせられるというのは、本人からすればストレスになりますので、ご本人の体調がよく、他の人がいない静かな場所で行うのが良いです。
2)この検査だけで認知症かどうか決めない。
数値を単独でみるのは誤解のもとになりますので総合的な判断が必要になります。
結果は本人の教養や生活環境で左右されますし、体調が悪い時、鬱っぽい時、せん妄状態などでも点数が低い場合があります。
認知症の検査は、一般所見、神経学所見をとり、血液・画像検査をします。また他の疾患(甲状腺機能低下症、慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症、鬱病)などが隠れていないかなど総合的にみていきます。
また長谷川式認知症スケールは、30点満点中20点以下を認知症の疑いとしますが、「21点だから大丈夫。20点以下は認知症です。」と100%区別する境界ではありません。あくまでも判定精度がもっとも高いという意味で理解されてください(感度93%、特異度86%)。
3)質問者が間違いやすい設問5「それから7をひくといくつでしょう?」
設問 5は計算問題です。
正しい質問の仕方は、「100 引く 7 はいくつですか?」と問い、「93」と答えが出たら、「それから7を引くといくつでしょう?」と聞きます。
間違った質問の仕方は、「100 引く 7 はいくつですか?」と問い、「93」と答えが出たら、「93から7を引くといくつでしょう?」と聞きます。
この質問は計算ができるかどうかを知りたいのではなく、「93」という数字を頭の中で記憶保持し、そして「7を引く」という作業を同時に並行してできるかどうかが知り得たい情報になります。
4)設問6は、ゆっくり1秒間隔!
設問6は数字の逆唱です。
はじめに「私がこれからいう数字を、逆から言ってください1 2 3」と伝えます。
数字は約1秒の間隔をおいて伝えて下さい。言い終わったところで逆から答えてもらいます。
時々、すごく早口で数字を「123」と伝える方がおられますが、これだと一つのまとまったワードで頭の中に入ってしまい意味合いが変わってしまいます。
5)小道具は、対象者にとって馴染みあるものを選びます。
施設や病院には、すでに小道具セット(鉛筆、カギ、スプーン、歯ブラシ、腕時計)が準備されているところが多いかと思います。
しかし高齢患者の中には、認知症とは関係なく「普段使わないから忘れた。」という方々もおられます。
施設に入るとカギは不要ですし、総入れ歯の方は、歯ブラシを使用していないこともあります。
すでにある小道具セット以外のものを使用してもよいですので、テストをうける方の馴染みのある物品が良いかと思います。
ただし注意点は、消しゴムと鉛筆など連想させるものは避け、関連性のないものが適しています。またタバコなど嗜好品は人によって集中力を欠きますので避けた方がよいです。
まとめ
認知症は早期発見が重要で、長谷川式スケールは判断材料の大切な一つになります。
早期に認知症とわかると、治療により進行を遅らせることができます。その分、ご本人の意志を尊重する生活を延長し、家族や介護者にあらかじめ心積もりする知識や準備時間が作れます。
検査結果は「この方は認知症です。」と選別します。しかし、結果の目的を判断材料としてだけでとらえず、認知機能の弱み強みをみつけて、家族を含め「より豊かな生活をするために」必要な情報として活用されてください。
下記の文献やサイトを参考に記事を作成しました。
認知症疾患治療ガイドライン2010 – 日本神経学会 https://www.neurology-jp.org/guidelinem/nintisyo.html
改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)http://www.medica-site.com/special/img_special069/hasegawa.pdf
ケアスタッフ
最新記事 by ケアスタッフ (全て見る)
- 入浴介助で水虫はうつるもの?介護のプロがしている白癬菌対策 - 2019年11月22日
- これって虐待?認知症ケアで後悔しないためのチェックリストと対処方法 - 2019年10月10日
- ナースが混同しやすい用語「自立支援介護」と「自立支援医療」の話 - 2019年7月10日
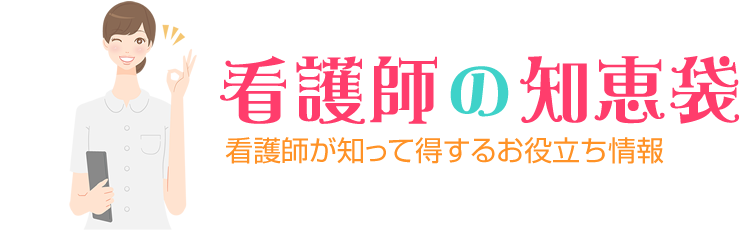
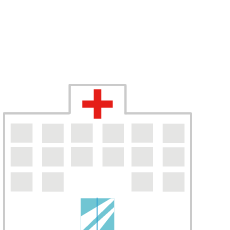


 職場を変えた話
職場を変えた話 看護力向上いいんかい
看護力向上いいんかい 看護のお悩み相談室
看護のお悩み相談室 ホット一息 トレンド広場
ホット一息 トレンド広場